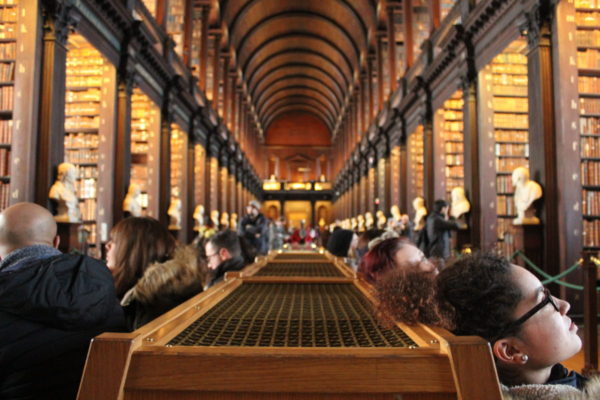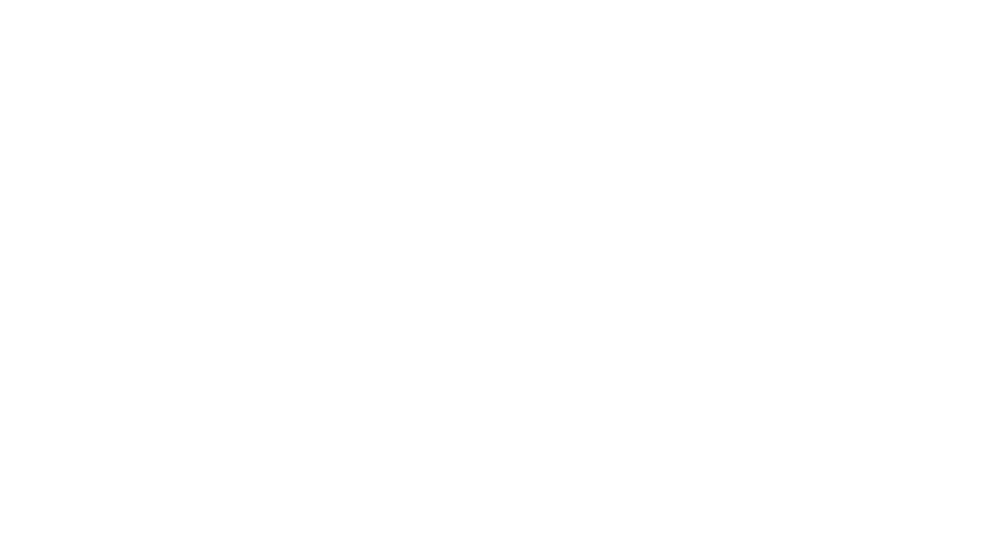こんにちは!アイルランド、ダブリン在住ウェブライターのハルノ(@haruno_sudo)です。
先日こんな記事を読みました。
「決断疲れ」を起こす人は「判断軸」を知らない
決断をすることが苦手な方が知っておくと便利な意思決定の仕方、が記事の内容です。
”一方、人生や仕事を左右するような大きな意思決定だけではなく、日常の中にも小さな意思決定がたくさんあります。これらに時間がかかってしまうと、重要なことを実行する時間が削られたり、決断に時間がかかることで自分や周囲がストレスを感じることにもつながるでしょう。
何かを決断するということは、かなりエネルギーを要します。
旅行ってつかれる…というのはこの典型でしょう。
普段はしない、意思決定をいくつもしなくてはいけない旅行中。
自分は何が好きで何を見たいのか?
ホテルはどんなところが良いのか?
交通機関は?
レストランは?
というかそもそもどこに行きたいか決められない…
みたいな感じで、決定しなくてはいけないシーンが多い旅行は疲労の元となることも。疲れたことがきっかけで一緒に旅行している人と大喧嘩…みたいなことを経験した人は少なくないはず。
そして、意思決定が疲れてしまうのは、決して非日常においてだけでなく、日常生活においても同じことが言えます。特に大きな決断をするときはプレッシャーがかかって不安になりますよね。
以前記事にも書いたように、私自信も意思決定するのが苦手な方で、人に流されていました。
最近では、
- 内定を辞退
- ワーホリで生活
- フリーランスのライターとして働く
という人生の転機となる大きな決断をいくつかしてきています。
決断を下すことが苦手だった私がこのような意思決定をするためには、いくつか意識して行ってきたことがあります。
<スポンサーリンク>
自分で決める習慣をつける
自分で意思決定をすることが出来ない人の多くは、人に流されることが習慣化してしまっていることが多いです。
そのため、まずは自分で決める習慣をつけることが必要。
大きな決断をいきなりするのはやはり勇気がいるので、小さなことから
例えば、
夕飯のメニュー、とか
週末に何をする、とか
家族や友人に『何でもいいよ』というのが口癖になっていませんか?こういう小さいことから自分で決定することを積み重ねることで、大事な時の決断も同じように行うことが出来ます。


規準を決めておく
先に紹介した記事のなかで、意思決定の仕方の一つとして、『評価軸を決めておく』という方法が紹介されています。
まずは評価軸を決めます。就職先であれば、給与、福利厚生、働きやすさ、将来性、自分のスキルとの適合度……など重視する評価軸と点数の基準を決めます。基準は100点満点としたり、5段階評価などが良いでしょう。
.
.
.重要なのは各評価軸の重み付けです。評価軸全てが同等に重要であることは稀ですから、給与が最も重要ならば50%の重み付け、次は将来性に20%、働きやすさが10%……などと、重要度のウェイトを決めます。こうすると各選択肢を総合的に評価することができます。
このように評価軸を決めておくのは意思決定において効果的です。日常生活で常に5段階評価をしろ、といっているわけではなく、
『このような状況に陥ったときにはこちらを選ぶ』
ということをあらかじめ決めておくと、迷わずに済みます。
ちなみにいまの私の大半の評価軸は『ワクワクするかどうか』
- 自分が楽しめるかどうか?
- これを共有して、皆が楽しめるかどうか?
などを基準としています。皆が楽しめるというのは、記事自体が楽しめるものや、記事を通して学んだことで、ワクワクできる生活を手に入れることができる、といったものなど。
人生を楽しみたい、という気持ちを選択でも表現するようにしています。
<スポンサーリンク>
やらないことも選択であることを知る
何かを選択するときって、何かを得るときと捉えられがちですが、『辞める』というのも意思決定の一つです。
何かを選択するときは、何かを捨てているということ。そのサイクルを理解すると、より意思決定がしやすくなります。
以前、ミニマリズムについて少し触れた記事を書きました。友人が自分に割いてくれた時間というのは、他のことに使える時間を削って、私と共有するということを選択してくれた、ということ。
堅苦しく思う方もいるかもしれませんが、そんなことを思いながら友人に感謝していました。
無駄なものを省いていって残ったものは、自分の大切なものなの。
そのため、自分で決断がなぜかできないと、悩んでいる方はまずは無駄なことを辞めてみることから始めてみたらいいかもしれません。


自分の為の選択であることを知る
そもそも何故自分が決断をするのが苦手なのか考えたことはありますか?私が意思決定を苦手としていた理由は、とにかく自分の決定に不安を感じていたから。
誰かにアドバイスを聞きまくって、結局自分の意見なんかなくて周りの意見で多くを決定していたんです。
自分に自信がないこともあって、誰かに背中を押してもらえないと不安でしょうがないんですよね。
でも気づいたのは、
- 他人は私の意思決定に関して責任を持てない
- 全ては自分のための意思決定である
ということ。言ってみれば当たり前なのですが、私の様に他人の意思決定に頼ってしまうときはこれを見失いがちなんです。
でも自分の決断は、自分が進む道を決めて、自分がどうあるかを形作る。誰もあなたの代わりをすることはできません。
最後は受け入れることを覚悟する
このように言っていても、やはり自分で決定したことはすべてうまくいくとは限りません。それに落胆してしまうこともあるかも知れませんが、それはもう受け入れるしかないんです。
村上春樹の作品、『海辺のカフカ』で私が好きなキャラクターの一人である、大島さんがこんな言葉を言っています。
『田村カフカくん、僕らの人生にはもう後戻りができないというポイントがある。それからケースとしてはずっと少ないけれど、もうこれから先には進めないというポイントがある。そういうポイントが来たら、良いことであれ悪いことであれ、僕らはただ黙ってそれを受け入れるしかない。僕らはそんなふうに生きているんだ。』
(海辺のカフカ、村上春樹/新潮文庫)
最後は受け入れて、次に進むしかない。どうしようもならないこともたくさん世の中には起きます。自分の思い通りにならなかったときに、
自分に嘆いて立ち止まってしまうのか?
踏ん張って次へとつなげることができるのか?
それは自分次第。
自分がした意思決定の結果生じた、どうしようもないことだと、受け入れることの抵抗は軽減されるし、次のステップにも進みやすいですよね。
一人でも多くの方が自分の納得いく意思決定をすることができるように祈っています。
<スポンサーリンク>
(photos/ Kununurra Australia)